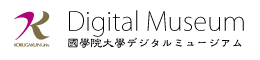- トップ
- 資料画像解説
資料画像解説
-
meigaku__RCMS_CONTENT_BOUNDARY__meiji__RCMS_CONTENT_BOUNDARY__aoyamasingaku__RCMS_CONTENT_BOUNDARY__keiohiyoshi__RCMS_CONTENT_BOUNDARY____RCMS_CONTENT_BOUNDARY____RCMS_CONTENT_BOUNDARY____RCMS_CONTENT_BOUNDARY____RCMS_CONTENT_BOUNDARY____RCMS_CONTENT_BOUNDARY____RCMS_CONTENT_BOUNDARY____RCMS_CONTENT_BOUNDARY____RCMS_CONTENT_BOUNDARY____RCMS_CONTENT_BOUNDARY____RCMS_CONTENT_BOUNDARY____RCMS_CONTENT_BOUNDARY____RCMS_CONTENT_BOUNDARY__
-
折口信夫博士(1887~1953)は国文学者・民俗学者・歌人として優れた業績を残した一方で、歌舞伎に関する著作(『かぶき讃』)を著すなど、歌舞伎愛好家としても知られる。國學院折口博士記念古代研究所には、博士が蒐集した歌舞伎を中心とした絵葉書・ブロマイド2547点が所蔵されており、明治から昭和前期にかけての我が国の伝統芸能とメディアのあり方を示すものとなっている。本データベースでは、絵葉書・ブロマイド2547点をデジタル化し、背面画像を含む5094画像を公開している。[文学・民俗]
≫國學院大學折口博士記念古代研究所
-
The online Encyclopedia of Shinto is the English translation of the Shinto jiten edited by the Institute for Japanese Culture and Classics and published by Kobundo in 1994 (the text as translated here reflects certain emendations to the original Japanese version). Links to video images, illustrations, photographs and sound files have been added anew. The original Shinto jiten is the most widely used general work of reference regarding Shinto in Japan today. It is our hope that by introducing the results of modern Shinto research through this medium, we will contribute in some way to the further growth of international research on Shinto and Japanese culture. We hope it finds use not only by scholars, but by students and others with an interest in Japan. This project is one element of the Kokugakuin University 21st Century Centers of Excellence Program, "Establishment of a National Learning Institute for the Dissemination of Research on Shinto and Japanese Culture" under the auspices and support of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology.
神道に関する語を英語で解説している事典。もともと國學院大學21世紀COEプログラム「神道と日本文化の国学的研究発信の拠点形成」事業の一環として行われた『神道事典』(弘文堂、1994年)の英訳プロジェクト(2005年公開)を引き継いだもので、2009年の國學院大學デジタル・ミュージアム稼働に際してデータを移行し、増補改訂を行ってきている。現在1480の項目があり、事項の項目には読み方を示す音声が付されている。また画像(223枚)、動画(155本)、図表(33枚)など、理解を助ける周辺情報をも含んでいる。[翻訳] -
英語版EOS(Encyclopedia of Shinto)を韓国語に翻訳したもの。現在、各部のIntroductionと、第4部「神社」・第8部「流派・教団と人物」、あわせて441項目が公開されている。[翻訳]
≫초보자를 위한 그림으로 보는 신도 입문 (図説による神道入門)
-
This booklet is a brief exposition of selected terms of Shinto. This is compiled for the convenience of historians of religions who have gathered to attend the IXth International Congress for the History of Religions. Shinto is a religion developed indigenously in the Japanese soil. So it is unique in many ways, its doctorinal formation and forms of rites and festivals. There are a good many words of Shinto which could not be adequately translated into European languages. Precise understanding of them would be invaluable help for the inquiry of religious life of the Japanese people. We shall be happy if this booklet is of any use to visitors who wish to study Shinto and observe the Shinto shrines.
神道の基本的な用語を英語で解説している用語集。もともと書籍として出されたものを1997年以来web上で公開しており、2009年の國學院大學デジタル・ミュージアム稼働に際してデータを移行した。より包括的なEncyclopedia of Shintoに対して、こちらではより簡潔な説明がなされている。326語の解説を収録し、一部には説明画像がある(70枚程)。[翻訳] -
このデータベースは、広く世界に向けた日本文化と宗教文化の発信を目的に、神社に関する画像コンテンツ〔社殿・祭りの空間を含めた神社景観、一部の祭り(神社祭礼)〕を公開するものである。画像とともに神社の基本情報を日本語と英語により表示することで、神社・神道についての国際的に教育・普及の深化を図っている。 なお、本データベースは「日本文化と宗教文化への理解を深めた人材を育成するミュージアム連携事業」の一環として「資料アーカイブによる教育・映像コンテンツ作成」に関わる画像・映像コンテンツを蒐集し、その成果の一部をデータベース化したものである。[翻訳]
This database holds photos of Shintō shrines. Currently available for public view are photos of the Nijūnisha(二十二社, the “Twenty-two Shrines” patronized by the imperial court during the Heian period). For further details about the Nijūnisha, please visit “Map, List and History of the Nijūnisha”.
≫Guide to Usage -
このデータベースは、広く世界に向けた日本文化と宗教文化の発信を目的に、神社に関する画像コンテンツ〔社殿・祭りの空間を含めた神社景観、一部の祭り(神社祭礼)〕を公開するものである。画像とともに神社の基本情報を日本語と英語により表示することで、神社・神道についての国際的に教育・普及の深化を図っている。 なお、本データベースは「日本文化と宗教文化への理解を深めた人材を育成するミュージアム連携事業」の一環として「資料アーカイブによる教育・映像コンテンツ作成」に関わる画像・映像コンテンツを蒐集し、その成果の一部をデータベース化したものである。[翻訳]
This database compises images of Shintō shrines. Currently available for public view are images of Ichinomiya form througout Japan(一宮, the "literally first shrine" regarded as the tutelary shrine for the entire province). For further details about the Ichinomiya, please visit "Map, List and History of the Ichinomiya".
≫Guide to Usage -
毎文社文庫は宗教学者の原田敏明(1893-1983)の資料図書類である。これらは氏の没後、母校である皇学館大学の神道研究所へ寄贈された。本DBは皇學館大学神道研究所『原田敏明毎文社文庫写真目録』として文字データの整理を行なったものに、共同研究として國學院大學日本文化研究所「劣化画像の再生活用と資料化に関する基礎的研究」プロジェクトで原田敏明写真資料の画像を電子化したものを加えたものである。ここでは暫定的に戦前期撮影分として3648の項目を掲載し、うち3555の画像を公開している。[国学・神道]
≫皇學館大學神道研究所 -
近世・近代の「国学」に関連する人物についてのデータベース。慶長年間より明治36年末までに物故した神道家、歴史家、歌学者、有職家、法律家などの「国学者」をはじめ、『和学者総覧』(國學院大學日本文化研究所編・発行、1990年)に所収される「和学者」(慶長年間の後半以降の物故者より明治元年までの出生者、漢学者・俳諧師・狂歌師等を含め、神学・歌学・歴史・有職等の学問に携わった人物)など、約12000人のデータを収録する。[国学・神道]
「国学関連人物データベース」は、國學院大學21世紀COEプログラムおよびその後継事業として、近世・近代の「国学」に関連する人物の情報を一般に公開するために作成されたものです。 ≫概要詳細
≫検索のしかた ≫詳細画面の項目
国学関連人物データベース一覧表(PDF) ≫あ行 ≫か行 ≫さ行 ≫た行 ≫な行 ≫は行 ≫ま行 ≫や・ら・わ行